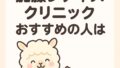2025年参議院選挙を前に、各政党が発表している子育て・妊活・教育政策をそのまま読みたい方のために、
公式資料や政策集に基づいた内容を、見やすく一覧でまとめました。
「子育て支援に力を入れているのは?」「妊活への具体策はある?」
そんな疑問に、政党自身の言葉で答えるページです。
選挙前の比較検討に、ぜひご活用ください。
本記事は子育て、妊活、出産に関わる情報を中心に、
各政党の政策集や公約から該当部分を抜粋し、そのまま掲載しています。
文章のつながりや文脈が前後で読みにくくなる箇所もありますが、
あくまで原文を忠実に引用している点について、あらかじめご了承ください。
リンクは、可能な限り
その政策や制度の公式ページ・出典先へ直接飛べるURLを貼っています。
内容の真偽・詳細は、必ず各政党や公的機関の資料をご確認ください。
各党の子育て政策比較(本文抜粋)
自民党
こどもまんなか社会の実現へ、切れ目ない子育て支援を進めます
- 子供・若者や子育て世代の視点に立ち、「こども家庭庁」を中心に、すべての子供・若者が健やかに成長でき、将来にわたって幸せに生活できる「こどもまんなか社会」を実現します。
- 妊娠前から、妊娠期、子育て期までを通じた包括的な切れ目のない支援を強化します。
- 抜本的に拡充した児童手当、高等教育費の負担軽減、男性の育休促進の取組み、住宅支援など、子育て支援のメニューを十分に活用いただけるよう取り組みます。
- 「こども誰でも通園制度」の本格実施、保育所の配置改善や保育士・幼稚園教諭の処遇改善、放課後児童クラブの量・質の拡充等を着実に進めます。虐待や貧困など、支援を必要とする子供やその家族に、よりきめ細かい対応を行います。
教育と文化の力で、人を育み、未来を築きます
- 経済環境による「教育格差ゼロ」を目指して、未来への投資を拡充し、高校授業料の実質無償化をはじめとする教育費の負担軽減を加速します。道徳、英語、専門人材育成などを通じて、自ら未来を切り拓く「ひと」を育てます。
- 少人数学級や部活動の地域展開、いじめ対策を進め、不登校や発達障害等すべての子供達が安心して学べる質の高い教育を実現します。改正給特法の確実な実施で志高い教師を確保します。

立憲民主党
社会全体ですべての子どもの育ちを支援し、希望する人が安心して子どもを産み育てることのできる社会をつくります。
綱領2-(オ)より抜粋
- 子どもの意見表明権や、性や生き方の自己決定権の尊重など、子の最善の利益を優先する「チルドレン・ファースト」を施策の中心に据えます。
- 育児休業給付の実質100%支給をめざすとともに、男女のワーク・ライフ・バランスの実現にむけて、誰もが必要に応じて育児休業や介護休業が取得できる制度への見直しを進めます。
- 児童手当の対象をすべての子どもとし、増額と支給年齢の延長を行うとともに、児童扶養手当の増額などひとり親家庭支援を強化します。
- 不妊治療をはじめ妊娠・出産・子育てへの支援を拡充します。
- 保育所と放課後児童クラブの待機児童解消をはかるとともに、すべての子どもに質の高い保育・幼児教育を確保して、これを無償化します。
- 小中学校の学校給食費無償化、所得制限のない高校授業料の無償化、大学授業料減免の拡充、給付型奨学金をはじめとする修学支援制度の大幅拡充によって、親の教育負担を減らし、子どもの貧困とその連鎖を防ぎます。
- 義務教育・高校教育における少人数学級編制と、きめ細かな教育を可能とする少人数学習を推進します。
- 児童虐待やいじめを受けた子どもたちの保護と、その防止対策を進めます。
- 社会的養護を必要とする子どもや、特別な環境にある子どもたちの教育を支援し、違いを認め合いともに学ぶ「インクルーシブ教育」を推進します。
- 学校教育におけるICTをツールとした教育を推進し、対面授業とオンライン授業の両立を支援します。

日本維新の会
3 教育・保育の無償化と質の向上 3-1 教育の無償化と質の向上 ⚫ 子どもたちが経済状況にかかわらず多様で質の高い教育を受けられるよう、義務教育に加えて幼児教育・ 高校を所得制限なく無償化します。大学・大学院は改革と合わせて、教育の全課程の無償化を目指します。 ⚫ 全国どこでも多様で質の高い教育機会を確保するため、都道府県毎に高校教育改革実行計画を策定 して地理的アクセスを確保しつつ、就学支援金の生徒への直接支給を行い、自己選択・自己決定でき る主体的な高校生の育成を目指します。 ⚫ 教育バウチャー制度を導入し、学校以外のさまざまな教育機会を拡大するとともに、教育分野においても市 場原理の下で多様なプレイヤーの競い合いによる質の向上を目指します。 ⚫ 学校給食法が定める給食の教育目的に鑑み、教育無償化の観点から小中学校給食を無償化し、食育を推 進するとともに、家計への経済的負担および教職員への徴収・管理業務負担の軽減を図ります。 ⚫ 教育無償化の一環として、複数の学校を受験し、最終的に1校に入学する際に発生する、他校への入学金支 払いによる経済的負担をなくすため、進学しなかった学校に支払った入学金を返還する制度を導入します。 ⚫ 大学無償化については、職業教育と学術研究との役割の明確化、教育内容の充実と国際競争力の高 い研究力の向上、大学入試改革、学習評価の客観性の確保、大学数の適正化やその他の大学改革を実 施した後に、授業料無償化の段階的拡充を目指します。 ⚫ 大学が「知の拠点」と同時に「ベンチャーの拠点」となるよう、国際卓越大学を 10 校化し、国 際競争を視野に研究力を強化します。人口減少の中で大学の規模の適正化を図り、地方でも高 等教育の機会を確保し、地域の特性を生かした産業ビジョンと連携した地方大学を目指します。 3-2 出産・保育の無償化 ⚫ 出産時の自己負担が子育て世代の家計や少子化の進展に深刻な影響を与えている現状に鑑み、出産にか かる医療費は原則保険適用とし、さらに「出産育児バウチャー」を支給することで出産費用を無償化します。 ⚫ 子どもの数が多いほど税負担が軽減される日本版「N 分 N 乗方式(世帯単位課税)」を導入するなど、税 制や社会保障制度からも子育てにかかる経済的負担を軽減し、進行する少子化の改善を図ります。 ⚫ 国家危機である少子化を克服し現役世代を活性化する観点から、子育て世代の「最初の大きな壁」となって 9 いる 0-2 歳の幼児教育・保育の家計支援を拡充し、未就学児も所得制限のない完全無償化を目指します。 ⚫ 子どものために使われる大規模な財源を確保し、予算枠を財務省の取りまとめから独立させ、GDP の一定 割合を必ず子どものために配分する等と定めた上で、その財源を着実に活用できる在り方を検討します。 3-3 誰もが働きやすい社会 ⚫ 世界一の長寿国である日本において、平均的な健康寿命が延伸している状況に鑑み、現役世代、すなわち、 生産年齢人口の定義を見直すことで、社会保障制度を持続可能にするとともに、社会の活力を取り戻します。 ⚫ 法律施行後も正規・非正規の雇用格差が残り実態の伴わない「同一労働同一賃金」を実現するため、国の 責務として、契約形態による年功序列型の職能給制度から、職務・職責による給与制度への転換を促します。 ⚫ 戸籍制度および同一戸籍・同一氏の原則を維持しながら、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効 力を与える制度の創設により、結婚後も旧姓を用いて社会経済活動が行える仕組みの構築を目指します。 ⚫ 育児や介護を理由とした離職を防ぐため、育児・介護支援のみならず家事支援サービスの利用促進を図る など、働きながらケアができる体制整備に努めます。 ⚫ 企業の女性雇用率や女性役員比率、男性の育児休業および出生時育児休業(男性版産休)取得率などに 応じて政策的な減税を行い、女性や子育て世代が活躍しやすい機会を増やします。

公明党
【子育てのトータルな安心を確保】
妊娠・出産から子どもが社会に巣立つまでの切れ目のない支援策を充実するために、公明党が提唱した「子育て応援トータルプラン」を踏まえ、児童手当の抜本拡充や妊娠・出産期の伴走支援、高等教育の無償化拡大などが着実に実現しています。子育ての不安を解消し、子どもを持ちたいと希望する人が安心して子どもを産み育てられるよう、さらに支援を充実し、子育てのトータルな安心を確保します。
・妊娠・出産の無償化、産後ケアの充実
妊婦健診や分娩費用など妊娠・出産に係る基礎的な費用を無償化するとともに、産後ケアの充実など安心して子どもを産み育てられる支援を強化します。
・こども誰でも通園制度
就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」について、保育人材の不足や利用時間等の課題の解消を図りつつ、地域の実情に応じた取り組みを進めます。
・不登校支援
さまざまな理由で不登校になっても、自分らしく多様な生き方ができるように、学びの多様化学校(不登校特例校)の全都道府県・政令指定都市への設置やスペシャルサポートルームの全小中学校への設置、フリースクールなどの安心できる居場所の確保に取り組みます。
不登校による保護者の離職防止のため、保護者の相談・支援の強化、企業における不登校の介護休業等の柔軟な働き方への対応、総合的な情報サイトの設置を推進し、不登校の児童・生徒と家族を社会で支えます。
・教育の質の向上
子どもたち一人ひとりにきめ細かい教育を実現するため、小中学校35人学級を推進し、将来的には小中学校30人の少人数学級をめざします。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの配置や、GIGAスクールの推進など、多様な子どものニーズに合わせ、柔軟な学びができ、子どもが生きる歓びに輝く公教育へ質の向上に取り組みます。
・仕事と育児を両立しやすい職場環境の整備
男女ともに着実に育児休業を取得できるよう、休業取得者の周囲の労働者への応援手当を支給する等、育児休業を支える体制を整備する中小企業への助成制度の利用を促進します。
1時間単位で有給休暇を取得できる制度や、フレックスタイム制度、テレワーク等の導入を促進し、子育てしやすい「柔軟な働き方」を推進します。
・「小1の壁」打破へ 放課後児童対策を強化
放課後における子どもの安心・安全な居場所を確保し、「小1の壁」を打破するため、「放課後児童クラブ」などの受け皿の拡大に取り組むとともに、開所時間の延長や夏季休業中の対応など待機児童対策の充実に向けた支援を強化します。

国民民主党
5. 出産・子育て支援策の拡充と所得制限撤廃
(1)児童手当の拡充・年少扶養控除の復活
日本の将来を支える子どもを等しく支援するため、親の年収にかかわらず、第一子、第二子の児童手当を18歳まで一律で月額1万5000円に拡充します。年少扶養控除を復活、高校生の親の扶養控除を堅持します。
(2)全ての障がい児福祉に係る所得制限撤廃
(詳細は政策各論3の11の(1)の❶障がい児福祉に係る所得制限の撤廃と手当の引き上げ)
(3)ひとり親家庭に係る所得制限撤廃
ひとり親家庭の養育費確保問題に取り組むとともに、児童扶養手当の水準を引き上げます。医療費等の所得制限等も撤廃します。
また、ひとり親家庭の生活の安定と向上に向け、副業・兼業者への労働時間・賃金の通算による社会保険等の適用に向け早急に取り組みます。
(4)多子家庭・多胎家庭への支援強化
多子家庭や多胎家庭は、育児や家計の負担が特に大きく、孤立しやすいリスクを抱えています。「安心・安全・安価・気楽」「使いたい時にすぐ使える」サービスの拡充を進めます。具体的には一時預かりや訪問型支援、移動支援、家事・育児ヘルパーの充実、きょうだい児の支援等、多様なニーズに応じた支援を柔軟に届けられる体制を整備します。
(5)公的給付金への非課税
「公的給付金非課税措置法案」の成立をめざします。出産や子どもの養育、教育等の公的給付等については、給付の効果が減殺されることがないよう所得税を課しません。
(6)男性の育児参画
男性を含め一定期間の育児休業機会の付与を事業主に義務化します。男女ともに育休中の賃金保障を実質100%とする雇用保険法改正を実現します。父母が互いに育児を支え合う夫婦協同育児(コペアレンティング)と子育てシェア等を推進します。
また、「育児休業」を「育児参画」に改称し、職場での男性の休みづらさを解消します。
育児休業者の代替要員確保等の支援を拡充します。
(7)待機児童・待機学童の解消に向けた保育環境整備と人材確保
待機児童の解消のため保育施設と放課後児童クラブ充実に向け、保育及び学童保育に関わる職員の賃金を引き上げます。併せて休日保育・学童、病児・病後児保育等多様な保育を充実させます。
(8)妊娠・出産に係る公費支援
不妊治療への公的支援やノンメディカルな卵子凍結(加齢により妊娠が困難になることに備え健康な若い女性が行う卵子凍結)についての助成をさらに拡充します。不妊治療に対する社会的認知を進めます。また、小児、若年性がん治療薬の妊孕性温存療法(精子・卵子保存)を保険適用にします。出産における麻酔の利用について、安全な無痛分娩を受けられる体制整備を行います。
(9)日本型ネウボラの創設
保健師・医師等による妊娠時から高校卒業までの「伴走型支援」を制度化し、妊娠・出産、子育て期まで保健や子育ての支援が一体となった切れ目のないサポート体制(ネウボラ)を構築します。子育て世代包括支援センターにおける業務を拡充し、妊娠時から高校卒業まで担当の保健師・医師等に相談ができる体制と組織を構築します。
6. 子どもの安全と福祉の確保
(1)児童虐待防止対策の強化
身体的虐待のみならず、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト等、全ての虐待から子どもたちを守るための多機関連携と伴走施策を進めます。
まずは児童養護施設や一時保護所、児童相談所スタッフの増員とデジタル化、専門職の配置のほか、子どもたちを取り巻く環境の整備が必要です。被虐待児の心身のケアと学習支援、虐待加害者等への生活支援、里親制度の更なる充実も併せて推進します。また、新たに法整備された「日本版DBS法」※を着実に実行するとともに、民間事業者にも性犯罪歴の確認を義務付け、子どもたちを性被害から守ります。
※日本版DBS法…幼稚園や小中学校等に就職希望者の性犯罪歴の確認を義務付ける法律
(2)子どもの死亡検証(チャイルドデスレビュー)の導入
医療機関や行政をはじめとする複数の機関・専門家が連携して、亡くなった子どもの事例を検証し、予防策を導き出すことで、子どもの死亡を少しでも減らします。
(3)ヤングケアラー対策
「ヤングケアラー支援法」の施行状況を検証しつつ、育児や介護、障がいのある兄弟のケアや通訳等を日常的に行っている子ども(ヤングケアラー)の実態調査を定期的に行い、効果的な支援の方法を調査研究するとともに、ヤングケアラーの子どもやその家族に対する福祉的・教育的な支援を行います。

日本共産党
18、子ども・子育て
子育て・子どもに「冷たい国」から「やさしい国」に
2025年6月
日本は、子どもと親に「冷たい国」です。
政府の国際調査で、日本は国民の過半数が「自分の国は子どもを産み、育てやすい国だと思わない」と答えた唯一の国です。その理由は、教育費が高すぎること、雇用が不安定なこと、子どもを産み育てることに対する社会の理解がないことなどです。教育費が完全無償で、親の働き方が安定しているスウェーデンでは、97%が「自分の国は子どもを産み、育てやすい国だと思う」と回答しているのと対照的です。日本が子育て・子どもに「冷たい国」になっている最大の責任は、子ども・子育ての予算を低水準のまま放置してきた政治にあります。
日本は、家庭予算も教育予算も、GDP(国内総生産)比でOECD加盟国の平均以下で、高学費、多人数学級、劣悪な保育条件、子どもの貧困などが改善されないままになっています。もともと子育ての負担は重いものなのに、基本的に「家庭の責任」とし、政治の責任を果たしてこなかったことは重大です。
2023年にこども家庭庁が設置され、政府は「こどもがまんなかの社会の実現を」と言います。しかし、真に「こどもがまんなかの社会」をつくるには、子ども予算の抜本増と、子どもの権利の保障に本気で取り組むことが必要です。
自民党・公明党政権は、軍事費を2023年からの3年間で3・3兆円増やし、石破首相のもとで2025年度は8・7兆億円となりました。27年度には11兆円規模にする計画です。その財源をまかなうためには、大増税か、社会保障と教育予算を削るかしかありません。大軍拡ではなく、教育・子育ての予算をこそ増やすべきです。
日本共産党は、日本を子育て・子どもに「冷たい国」から「やさしい国」に変えるために、広い国民の皆さんと手をたずさえて、力を尽くします。
子育て、教育にかかわるお金の心配を減らす
世界では、学費の無償化を段階的に進め、多くの先進諸国で学費は大学まで無償です。しかし日本では、子育て・教育にお金がかかりすぎることが、親にとって最大のストレスとなっています。思い切って予算を増やし、子育てにかかわるお金の心配を減らすべきです。
――大学・短大・専門学校など高等教育の「学費ゼロ」にむけて、高等教育予算を抜本的に増額し、①ただちに授業料半額・入学金ゼロ、②給付中心の奨学金の創設、③奨学金返済の半額免除を緊急に行います。
➡詳しくはこちらをお読みください。アピール「学費値上げを許さず、値下げにふみ出し、『学費ゼロ』の社会にむけて力を合わせよう」(2024年10月2日)(https://www.jcp.or.jp/web_policy/2024/10/2024gakuhi-ap.html)
――国の就学支援金による高校授業料への支援は、私立高校の授業料には足りていません。国の責任で、高校授業料を無償化します。入学金、施設整備費等も無償にします。
――「義務教育は無償」とうたった憲法26条を踏まえ、国の制度として、学校給食費や教材費などを無料にします。「隠れ教育費」といわれるさまざまな負担を見直し、保護者負担を減らします。
――「幼保の無償化」(2019年から実施)は、対象が3~5歳と、住民税非課税世帯の0~2歳児に限られており、0~2歳の保育料、3歳以上の給食費が子育て世帯の負担となっています。所得制限なく、幼児教育・保育の無償化をすすめます。0歳~就学前のすべての子どもの給食費の無償化をすすめます。
――児童手当は2024年10月から所得制限が撤廃され18歳まで(*18歳の誕生日以後の最初の3月31日まで)広がりましたが、さらに拡充を進めます。「異次元の少子化対策」だとして「第3子以降3万円」となっていますが、第1子から拡充すべきです。
――国の制度として18歳まで医療費の窓口負担を無料にします。
――就学援助を国庫補助にもどして拡充します。
――ひとり親世帯は約134万世帯にのぼり、2021年のひとり親世帯の子どもの相対的貧困率は44.5%にのぼります(厚生労働省2023年「国民生活基礎調査」)。児童扶養手当は子ども3人以上の世帯で加算部分の支給額が引き上げられましたが、第1子から抜本的に改善し、所得制限の見直し、多子加算の引き上げなど拡充します。年6回の支払い回数を毎月支給へさらに改善をすすめます。現行18歳までの支給を20歳未満にします。支給開始5年後に半減する措置をやめさせます。
――離婚後の養育費問題などの解決をはかります。
――子育て世代向けの公共住宅の建設や「借り上げ」公営住宅制度、家賃補助制度、生活資金貸与制度などの支援を特別につよめます。
――妊娠・出産にかかる経済的負担の軽減をはかります。出産一時金の金額を大幅に引き上げます。国民健康保険の加入者にも出産手当金を支給する制度をつくります。
➡各分野の政策「66、教育」、「19、子どもの権利」もごらんください。
学校、幼稚園、保育園など、子どものための”人”をふやす
子どもを育てるには、多くの専門家が必要です。しかし日本では、学校、保育園、児童相談所など、子どもにかかわるあらゆるところで、圧倒的に人が足りていません。専門職にふさわしい処遇が必要です。
――教員不足は社会問題になるほど深刻化しています。授業数に見合った教員の定数増をすすめます。小学校・中学校すべての学年で早期に30人以下の少人数学級を実現します。
――幼稚園、保育園、認定こども園、学童保育など、子どもにかかわる施設の職員を、処遇改善と配置基準等の引き上げによって増やします。職員一人当たりの業務の軽減をはかります。定員が割れても職員を減らさず運営できるようにし、ゆとりある幼稚園・保育環境をつくります。小学校入学とともに保護者が仕事を辞めざるを得ないなど、いわゆる「小一の壁」が大きな社会問題になっています。学童保育に入れない子どもがたくさんいます。指導員を国の責任で増やし、学童保育を拡充します。
――児童相談所、児童養護施設などの体制を拡充します。
――子育ての不安を解消する相談支援体制を強化します。
初めての出産による不安や、失業、生活苦など、さまざまな問題を抱えた家族に対し、産前・産後サポート事業などきめ細かな相談体制、個別の訪問活動などの支援を拡充します。保育所への入所や一時保育、子育て支援事業など、子育て不安を軽減する取り組みを、病院や自治体の関係機関の連携をつよめ、地域全体ですすめます。そのための専門職員の配置・増員と予算確保を国の責任で行います。
➡➡くわしくは、各分野の政策「66、教育」、「21、保育」、「22、学童保育」、「19、子どもの権利」をごらんください。
安心して子育てできる働き方を保障する
「夫は帰りが遅く、家事も育児も私のワンオペ」、「仕事も子どもも大事にしたい。これはわがまま?」―日本では多くの親が、仕事と子育てとの両立に悩み、子育てを苦しくしています。背景には、「家のことは誰かに任せ、仕事に没頭できる」人を、働き方の標準にしてきたことがあります。
――長時間労働をなくし、賃上げと一体に「1日7時間、週35時間労働」を導入します。仕事と家族ケアを両立できる働き方のルールをつくります。
➡詳しくはこちらをごらんください。「賃上げと一体に、労働時間の短縮を働く人の自由な時間を拡大するために力を合わせましょう」(2024年9月20日)(https://www.jcp.or.jp/web_policy/2024/09/post-987.html)
――だれでも安心して利用できる育児・介護休業制度へ改善をすすめます。収入減少への不安で取得できないことがないよう、育休中の休業補償は、1年間は休業前の手取りの所得を補償する水準に引き上げます。制度利用による不利益扱いを許さず、原職復帰原則の確立、苦情処理・救済制度の拡充、指導・監督の徹底、違反企業への罰則強化などをはかります。非正規ワーカーが取得しにくい要因となっている「子が1歳6カ月になるまで雇用が継続している」という取得要件を撤廃します。
――男性の育休取得率は30.1%(2023年厚労省・雇用均等基本調査)になりましたが、取得日数は短く、ギリギリの人員で業務を回す働き方などが障害になっています。代替要員の確保、フリーランスの収入減少への支援、中小企業への助成拡充などを通じて男性の育休取得を進めます。
――子育てなど家族的責任をもつ労働者の残業は、本人同意を原則とします。単身赴任や長時間通勤を伴う転勤は、本人が希望する場合以外は原則禁止します。
――短時間勤務制度は、子どもが小学校入学前まで申し出により利用できるようにし、所得保障を充実します。時間外労働や深夜労働の免除も中学校入学前まで請求できるようにします。これらの措置が、昇給昇格において不利益な評価とされることを禁止します。
――「子ども看護等休暇」は、取得理由・対象を広げて「家族休暇」制度とし、両親が各年10日以上に拡充し、所得保障を導入します。対象を中学校入学前までひろげます。
――不登校が急増する中、親の「不登校離職」が大きな社会問題です。子どもの休養と回復を支えるには、親への支援が必要です。不登校は介護休業(通算93日まで、賃金補償あり)の対象です。周知徹底し、子どもに適した取得要件とし、活用しやすくします。介護休業制度を1年間に延長し、育児休業と同様に社会保険料の本人負担を免除、休業中の給付の拡充などをすすめます。年単位の「不登校休業制度」をめざします。
子どもの権利が保障される社会に
子どもの権利が保障される国づくり、地域づくりをすすめます。
→詳しくは、「19、子どもの権利」をご覧ください

れいわ新選組
4子ども・ジェンダー
どんな生まれであっても、すべての子どもたちの育ちと学びを保障する。それが政治の責任である。そして、すべての子どもたちは、その意志と、子どもとして生きる権利を尊重されなければならない。
日本のジェンダーギャップは先進国最低レベル。世界的に見ても男女の格差が大きすぎる。女性管理職や政治家は異常に少なく、男女の賃金格差、教育格差は大きい。この現状を改善するためには、男性や家制度が中心の法律や制度を構造的に改革する必要がある。同時に構造改革によって取り残される人がいないよう、現実的で無理のない意識改革をすすめていく。私たちは、「構造改革」と「意識改革」の2本柱で、個人の意識を変えながら、構造的な差別をなくしていく。
子どもたちが大人になる前に、すべての人が尊重される社会を、力を合わせてつくっていこう。
4-1子ども政策 子どもを真ん中に置いた社会を実現する
生まれにかかわらず、すべての子どもたちが育ちと学びを保障される社会を実現します。そして、すべての子どもたちが、その意志と子どもとして生きる権利を尊重される社会を目指します。
・子どもの貧困をなくすため、すべての子どもに所得制限なしで毎月3万円を給付する
・子ども手当導入の際に廃止された「年少扶養控除」を復活させる。「扶養控除」は維持する
・子どもの発育と食育を支えるため、小中学校の給食無償化及び導入をすすめる
・親族等のケアを担っている「ヤングケアラー」に必要なサポートを提供する
・子どもの主権の観点から校則を見直すとともに、体罰やいじめのない学校を実現する
・孤立を防ぐために、あらゆる人々が利用できる自治体やNPOの「居場所」づくりを支援する。子どもから高齢者まで、多様な世代の人々と交流できる、家でも学校でもない場づくりをすすめる
・児童虐待問題についての取り組みを強化し、一時保護など司法関与の強化と、家庭裁判所人員の増員をすすめる
・芸能界などにおける児童労働・性的搾取・人間的発達を犠牲にしたトレーニングなどの実態を調査し、被害者の救済措置制度を設けるとともに、人権方針を策定するなどの改革を促す
・国連子どもの権利条約が要請する「子どもの意見表明権」を保障するため、弁護士など第三者による「子どもの手続代理人(子どもオンブズパーソン)」制度の活用推進を国に求め、子どもの意見表明の権利を支援する
・児童相談所の職員の増員と研修などの質の向上、虐待児童の保護を担う介入部門と、児童の支援を行う支援部門の明確な機能分化を行う。また支援枠における専門職(児童福祉司や児童心理司など)の体制強化をすすめる。専門性を持った職員は「異動のない常勤公務員」として採用・育成し、虐待児童を支える体制を作る
・虐待を受けた子どもの、保護者との関係性修復や保護者への支援に加えて、家庭復帰後の継続的な支援を行う。そのために、ファミリーグループ・カンファレンス等のプログラムを通して、当事者の子ども、保護者、親族、専門職、地域の関係者が話し合い、家族を支えるインフォーマルな関係づくりを担う取り組みをすすめる
・家庭復帰が難しい場合は、施設入所措置や里親委託等の措置を、裁判所や第三者機関が行う。家庭復帰の可能性があるケースには、裁判所などの第三者機関が家庭復帰までの道筋を示し、支援する
・里親への研修、サポート、処遇を大幅に改善するとともに、里親になる要件について、単身者やまだ数少ない同性カップルの里親が増えるよう支援を行う
・虐待やDVの被害者をさらに追い詰める可能性のある離婚後共同親権については導入を見直す
・施設において、社会的養護下にある者の高校・大学等への進学で必要な授業料や諸経費、また運転免許取得費用等、自立を支えるための経済的支援を強化する。施設を出たのちも、賃貸契約や雇用契約などの契約について、継続的に子どもの保証人ないし保護者を務める人を行政の支援で指定するほか、こうした契約で親権者の有無が障害とならないよう措置を講じる。また保証人がいなくても住む家を確保できる制度づくりをすすめる
●インクルーシブ教育
・インクルーシブ教育・保育を推進し、障害の有無や、民族性、性自認などの違いが、子どもたちの相互理解を高め多様性を認め合う保育所・学校づくりを目指す
・現行の特別支援教育から、障害の有無で分け隔てられることなく共に学ぶインクルーシブ教育へ転換するための、具体的な達成目標、期間、予算を伴った行動計画を採択する
・授業や学校活動における合理的配慮を提供できるよう、人材の育成・配置をすすめる
・就学前からインクルーシブ保育・幼児教育を推進する。保育士・教員の加配、医療的ケアに対応できる人材の配置等、環境整備等への支援をすすめる
・障害児の就学先を教育委員会が判断・決定する現在の就学先決定のしくみを根本的に変え、どの子も地域の普通学校で学ぶことができるようにする。その上で、特別支援学校を希望する場合は、私立学校・民族学校等を希望する場合と同様に、学籍変更の手続きを行えるしくみにする
・特別支援学校在学の児童・生徒が居住地(通学区域)の学校へ転校を希望する場合の支援を拡充する
・高等教育における障害学生にとっての障壁をなくすために合理的配慮をすすめる
4-2子育て・教育政策 大人の都合で縛るのではなく、子どもの育ちに寄り添う保育・教育を
OECD諸国の中でも最低水準の子育て・教育予算を倍にし、包括的な公的子育て支援と、大学院までの教育費無償化を実現します。大人の都合を優先した規則や制度を押し付けるのではなく、子どもたちの育ちに寄り添う保育・教育を目指します。
・保育所、幼稚園、こども園、そして学童クラブといった形態にかかわらず、包括的な公的子育て支援を充実させる
・子どもの育ちや学び、ヤングケアラーなどの問題を所管する官庁を一元化し、縦割り行政による弊害をなくす
・奨学金徳政令で、奨学金返済に苦しむ約580万人の借金をチャラにする。すでに返済した人に対する合理的補償を検討する
・一部の「谷間世代」だけが司法修習の給付金を受給できなかった不平等を是正するため、財政措置を行う
・幼児から大学院生まで、保育・教育は完全無償化する
・大多数が高校に進学する現在、高校は希望者全入にする。最低でも公立高校の定員内不合格はなくす
・高等教育への公的支出については、最低でもOECD平均の4.0%を上回る財政規模を確保する
・夜間学校や二部授業の復活など、何らかの事情で学びを断念した人が学べる機会、学び直せる機会を保障する
・教員の待遇・労働条件を改善するとともに正規教員の数を大幅に増やし、現在進行中の深刻な教員未配置問題を解決する
・さらなる少人数学級化をすすめる。短期的には学級編成の基準をOECD平均並みの小学校25人、中学校30人以下を目指し、中長期的には20人以下学級の実現を目指す
・教員の成果主義や給与査定を禁止する。教員の多忙・長時間労働を解消し、教員が本来業務に専念するため正規教員、スクールソーシャルワーカー、スクールサポーター、部活動指導員等を増員する
•新型コロナ感染症拡大を受けて広まった「遠隔授業」について、通信費やPCなどの設備面の支援を行う
•フリースクールやコミュニティスクール、民族学校など、多様な「学校」を認め、公的に支援する
•大学の基礎研究に財政投資を行う。国立大学の運営費交付金を拡充し、成果主義的な研究費助成の割合を大幅に下げ、長期的な視点で研究に取り組めるようにする
・私学助成については、私立学校振興助成法の附帯決議にあるように、経常費補助率を50%に引き上げ、国立大学との公私間格差を是正する
4-3ジェンダー平等 性による差別のない社会へ
労働・教育の男女格差をなくします。女性が多くを担う、出産・育児・介護が「足かせ」になることがないよう、国が支えるしくみをつくるとともに、意志決定の場に女性を増やすことで、ジェンダーによって不公平が生まれる構造をなくします。
・非正規雇用の7割を女性が占める現状を鑑み、男女の賃金格差の是正になっていない「同一労働同一賃金」制度を見直す。罰則規定を導入し、非正規労働に不利となる給与の活用係数計算を改める
・男女の賃金格差の要因となっている、退職金や家族手当など福利厚生も含めた詳細な規定と罰則を設け、企業が改善できる状況づくりや経済的支援を実施する
・総合職・一般職の区分けによって女性が不利な状況に置かれている現状を改善するため、コース別雇用管理を廃止する
・産休と育休の給与補償に対する国庫負担割を引き上げ、現在の3分の2から100%の補償を実現する。また産休・育休が昇給・昇進の障害とならないよう規制を明確にすることで、男女の育休取得状況を改善する
・中小企業・個人事業者に対して、育児休暇取得にかかる財政や人材補充の支援を行う
・離職中の女性のキャリアを活かす復職支援や、職業訓練、資格取得の支援を拡充する
・育児手当・介護手当を国が創設し、家庭内のケアワークを適正に評価する
・保育施設や介護施設を拡充し、保育や介護従事者を公務員化するとともに、給与を月額10万円引き上げる
・学童保育指導員の給与や待遇を大幅に改善する
・制度やルールを決定する場に女性を増やすことで、ジェンダーによって不公平が生まれる構造をなくし、男女共に働きやすい環境整備を行う。政党は候補者及び役員の、公的機関は各種委員会や審議会委員の、大企業は管理職や役員の50%を女性に割り当てるクオータ制を法制化する
・すべての労働者が定時に帰宅できるよう、定時以降の残業代を5割増しにする等の罰則規定を設ける
・ジェンダー平等に取り組む企業に対して、補助金や税制などの優遇措置を行う。ジェンダー平等の推進を支援の対象に含め、その場合は支給基準となる要件を設定する
・女子生徒が入試で不利になる公立高校の男女別の定員(受験枠)の撤廃を目指す
・進路指導において「男は理系、女は文系」、「女性は手に職を」といったジェンダーの固定概念を与えないよう、進路指導をする教員に対する研修を実施する
4-4性の自己決定と多様性の尊重 多様な性を互いに尊重し合い、自己決定できる社会へ
からだや性についての学ぶ機会を保障することで、多様性を尊重するジェンダー「意識改革」をすすめます。そして、女性をはじめ、すべての人が自分のからだや性を自分で決定する権利を守ります。
・性に関する、精神面のケアを行うカウンセリングを保険適用にする
・中絶を自由診療ではなく、保険適用とする
・子どもを持つことが経済的負担とならないよう、すべての人が不妊治療の選択ができる環境を整備する
・出産費用や出産前後の支援をさらに拡充する
・出産時の麻酔利用を保険適用とし、無痛分娩が選択肢のひとつとなるようにする
・「生理の貧困」をなくすため、庁舎や学校、公共施設で生理用品を無料かつ申請なしに入手・利用できるように設置する。現行消費税制度の間は生理用品に軽減税率を適用するよう求める
・「性教育」は権利である。現行の性教育には含まれない、オーガズム・性交・多様な避妊方法・生理・中絶などの事象も発達段階に即して学ぶ。また、健康な人間関係を築くための情報収集の仕方・意見形成や意思決定の仕方・他者の尊重等を学ぶ
・「ジェンダー教育」を義務教育の一環とし、性の在り方に対する思い込みや押し付けを減らし、LGBTQ+(多様な性)、ルッキズム(外見に基づく差別)、ボディシェイミング(他人の体形を蔑む)などについて理解を深める
・性教育とジェンダー教育を各種団体や企業に対して提供する
・女性の性と生殖に関する自己決定権を尊重し、「配偶者の同意」を必要としない中絶の権利を求める
・妊娠中の女性が堕胎した際に刑罰に問われる、刑法堕胎罪を廃止する。同時に、遅れている日本の中絶技術を改善し、中絶した女性へのメンタルケアにも配慮する
・緊急避妊薬の薬局での販売を実現する
・国際的な人権基準に基づいた「LGBTQ+差別解消」を目的にする法律を速やかに法制化する
・同性婚を法制化する
・選択的夫婦別姓を実現する
・公的機関が発行する証明書(免許証やパスポート)において、性別欄にノンバイナリー(男女以外の性自認)を選択できるようにする
・配偶者のいる夫婦に限定されている特別養子縁組、どのような形態のカップルもしくはひとり親でも利用できるよう支援する
・各種支援金などが世帯ごとではなく個人に配布されるようにし、DV被害者や虐待被害者に対して、支援が行き渡らない現状を改善する

参政党
日本人を育む
〜教育・
人づくり〜
政策
偏差値重視の管理教育から
“愛と勇気を育む”人格形成教育に変える。
現代の日本の教育制度は、長年にわたって偏差値中心の競争型教育が続けられてきました。このような画一的で管理的な教育環境は、子どもたち一人ひとりの個性や可能性を伸ばすのではなく、順位や成績で評価される社会への適応を強いるものであり、多くの子どもたちが自信や自己肯定感を失っています。参政党はこうした教育のあり方を根本から見直し、「愛と勇気を育む人格形成教育」への転換を提案します。
近年の調査では、日本の若者の自己肯定感や社会参加意識が国際的にも低い水準にあることが明らかになっています。これは、単に学力や能力の問題ではなく、教育によって自国や自分自身に誇りを持てない環境が続いていることに起因します。参政党は、子どもたちが自らのルーツを学び、日本という国の歴史や文化に誇りを持てる教育を実現することが、社会を支える意識ある人材の育成につながると確信しています。
そのために、学校教育の中で神話や日本の建国の歴史、先人たちの生き様を学ぶ機会を増やし、単なる知識の習得ではなく、精神的な成長とアイデンティティの形成を重視します。また、郷土の偉人や伝統文化、地域社会とのつながりを学ぶことで、地元を愛する心=愛郷心を育み、それがやがて愛国心へとつながる教育環境を整えます。
さらに、家庭の大切さや家族のつながりを見つめ直し、家族愛や思いやりを学ぶ教育も導入します。家庭が社会の最小単位であるという意識を育てることが、健全な社会形成に不可欠であると考えます。このように、知識や技能の詰め込みではなく、「どのような人間になるか」を重視する教育に改革することで、子どもたちは自信を持って社会に羽ばたくことができるのです。
参政党は、偏差値や点数に縛られた教育から脱却し、日本人としての誇りと他者を思いやる心を育む新しい教育のかたちを実現してまいります。
政策
安心して子育てできる経済支援。
0~15歳に月10万円の教育給付金を支給する。
少子化が進む日本において、子育てや教育にかかる経済的負担の重さが、家庭に大きな影響を及ぼしています。教育格差は経済格差から生まれ、未来の可能性を奪う大きな障壁となっています。参政党は、すべての子どもが家庭の経済状況に左右されることなく、質の高い教育と安心できる子育て環境を受けられる社会を目指し、「子ども一人につき月10万円の教育給付金」を提案します。
この給付金は、0歳から15歳までのすべての子どもを対象とし、学校や施設ではなく「子ども本人」に対して直接支給されます。これにより、各家庭が子どもの教育や生活に必要な費用を柔軟に使えるようになり、保育、習い事、教材、学用品など、多様な育児ニーズに対応可能となります。財源には「教育国債」を活用し、未来への投資として国全体で子どもを育てていく仕組みをつくります。
また、奨学金制度の改革にも取り組み、返済不要の給付型奨学金の拡充や、公務員として社会に貢献する若者への返済免除制度など、多様な進路と支援策を整備します。これにより、大学進学を諦めることなく、自分の可能性を信じて挑戦する若者を社会全体で後押しする環境を構築します。
教育や子育てを「自己責任」にせず、社会全体で支え合う構造に変えることが、未来の日本を支える子どもたちのために今、最も必要な改革です。特に日本国籍を有する家庭を優先対象とし、真に支援を必要とする家庭へと行き渡る制度設計を徹底します。これによって、経済的事情で進学を断念するようなことがない、誰もが夢を描ける教育環境が実現します。
参政党は、「すべての子どもが希望を持ち、家族が安心して子育てできる日本」を創るため、力強い経済支援を実行してまいります。

社民党
少子化・低賃金・高負担に苦しむ若者世代に、公的支援を拡充します。大学までの教育費無償化をめざし、当面は給付型奨学金と返済免除制度を導入します。国籍や障がいにかかわらず、すべての子どもが学べる環境を整えます。出産への保険適用、子ども医療費と保育料の無償化、年少扶養控除の復活を実現。性別を問わず、誰もが子育てと仕事を両立できる社会をめざします。

日本保守党
8.教育と福祉
- 教科書検定制度(特に歴史)の全面的見直し(現行制度の廃止)
- キャリア教育の拡充、専門学科(商業科、工業科・高専、農業科など)の無償化。
- 思春期の自殺防止対策(「一人の子も死なせない」――内申書制度の改善、スクールカウンセラー導入促進など)
- 少子化による「大学余り」の解消。補助金を減らし統廃合促進。
- 留学生制度の見直し(安全保障の観点から出身国を厳選する)
- 男女共同参画事業に関する支出の抜本的見直し。
- 出産育児一時金の引き上げ(国籍条項をつける)
- 共同親権制度の導入(民間法制審案を軸に)

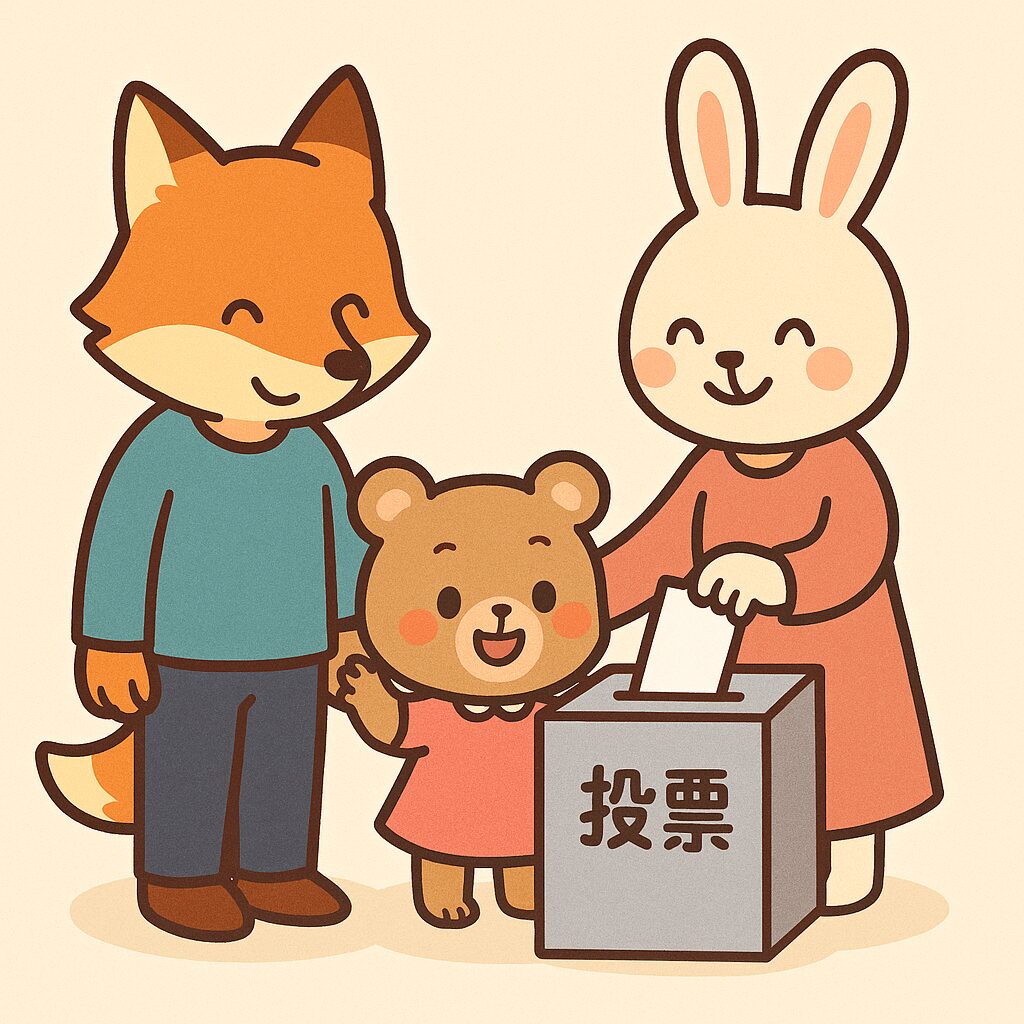
各党が掲げる政策は、それぞれに理念や優先順位の違いがあります。
この記事ではあえて比較せず、一次情報としての政党の主張をそのまま紹介しました。
あなたと家族の価値観に合う政党を見つけるため、
ぜひじっくり読んで、自分の目で選ぶ一票を考えてみてください。